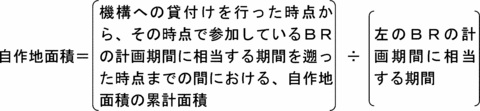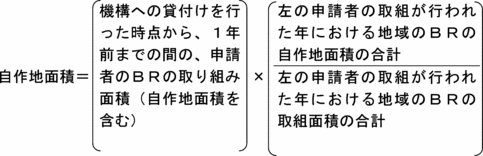���P�q�{���@�\�W�ϋ��͋���t���Ǝ��{�v��
�P�q�{���@�\�W�ϋ��͋���t���Ǝ��{�v��
�_�Ƃ̐��Y�������߁A�����͂��������Ă������߂ɂ́A�S����ւ̔_�n�W�ρE�W�𐄐i���A���Y�R�X�g���팸���Ă����K�v������B
���̂��߁A�{���Ƃɂ��A�_�n�̒��ԓI�M�ƂȂ�
�_�n���ԊǗ��@�\�i�ȉ��u�@�\�v�Ƃ����B�j�ɑ��_�n��݂��t�����n��y�ьl���x�����邱�Ƃɂ��A�@�\�����p�����S����ւ̔_�n�W�ρE�W�𑣐i���邱�ƂƂ���B
�Ȃ��A�{���Ƃ̎��{�Ɋւ��ẮA�@�\�W�ϋ��͋���t���Ǝ��{�v�́i����26�N�T���V���t���o�c299���k�C���_�������ʒm�j�ɒ�߂���̂̂ق��A���̗v�̂̒�߂ɂ����̂Ƃ���B
�{���Ƃɂ�����e�p��i���̕����j�̒�`�́A
�ʕ\�P�̂Ƃ���Ƃ���B
�{���Ƃ̑Ώ۔_�n�́A�P�q�{������
�_�ƐU���n��̋����̔_�n�Ƃ���B
�n����̔_�n�̈�芄���ȏ���@�\�ɑ݂��t�����n��ɑ��A���ɂ�苦�͋�����t������̂Ƃ���B
�ȉ��̗v�������u�n��v�Ƃ���B
(�P)�@�P�q�{�����̈����ł���A�S�悪����̐l�E�_�n�v�����̃G���A�Ɋ܂܂�Ă��邱�Ɓi���̊O�������m�ł���ꍇ�Ɍ���B�j�B
(�Q)�@�ȉ��̂����ꂩ�ɊY��������̂ł��邱�ƁB
�A�@�_�ƏW���A�厚���͊w�Z�擙�A�l�E�_�n�v�����̍쐬�E���s�̂��߂̎�����̘b�����̒P�ʂƂȂ��Ă�����́B
�C�@�A�ɂ�肪�����ꍇ�ɂ�30�����ȏ�̂܂Ƃ܂�̂���_�n�Ől�E�_�n�v�����̍쐬�E���s�̂��߂̎�����̘b�����̒P�ʂƂȂ��Ă�����́B
(�R)�@�\���ː��������˂ł��邱�ƁB
(�S)�@�_�n�ʐς��_�n�䒠�ɂ�薾�m�ł��邱�ƁB
(�P)�@�{���͋��̌�t���������u�n��v�́A�P�̗v�������ꍇ�ɂ͍������邱�Ƃ��ł�����̂Ƃ���B
(�Q)�@�{���͋��̌�t�����u�n��v�ɂ��ẮA���߂Č�t�����ۂ́u�n��v���Q��ڈȍ~�̌�t�z�̎Z��ɗp������̂Ƃ���((�P�j�̏ꍇ�ɂ́A������́u�n��v�����̔N�x�̎x�����̎Z��ɗp������̂Ƃ���B�j�B
�A�@���N�x�ɏ��߂Č�t�v���������ꍇ
�ȉ��̌�t�P���ɋ@�\�ւ̑ݕt�ʐς��悶���z
(�A)�@�u�n��v�̔_�n�ʐρi�_�ƐU���n��̋����̔_�n�Ɍ���B�ȉ��R�ɂ����ē����B�j�ɐ�߂�e�N�x��12�������_�ɂ�����@�\�ւ̑ݕt�ʐρi�ȉ��u���v�ʐρv�Ƃ����B�j�̊������Q�����T���ȉ�
(�C)�@�u�n��v�̔_�n�ʐςɐ�߂鍇�v�ʐς̊������T�����W���ȉ�
(�E)�@�u�n��v�̔_�n�ʐςɐ�߂鍇�v�ʐς̊������W����
�C�@�O�N�x�܂ł̂����ꂩ�̔N�x�Ɍ�t�v�������Ēn��W�ϋ��͋�����t����Ă���A���A���N�x���܂���t�v���������ꍇ
(�A)�@���N�x�̍��v�ʐς��O�N�x�܂ł̒n��W�ϋ��͋��̌�t�Ώۖʐς̍ő�l�i�ȉ��u�]�O�ő�ʐρv�Ƃ����B�j�ȏ�ł���ꍇ
���v�ʐς���]�O�ő�ʐς��������ʐςɃA�ɒ�߂��t�P�����悶���z
(�C)�@���N�x�̍��v�ʐς��]�O�ő�ʐψȉ��ł���ꍇ
�E�@�Ȃ��A����26�N�x�ɂ��ẮA�����ɋ@�\�֑ݕt���s�����u�n��v�ɑ������Ɍ�t���s�����߁A���v�ʐς̔c�����U������12�����̂Q��s�����̂Ƃ���B���̏ꍇ�A�P��ڂ̌�t�z�ɂ��Ă̓A�A�Q��ڂ̌�t�z�ɂ��Ă̓C�ɏ����ĎZ�肷����̂Ƃ���B
(�Q)�@����28�N�x�y��29�N�x�̌�t�z
�A�@���N�x�ɏ��߂Č�t�v���������ꍇ
�ȉ��̌�t�P���ɍ��v�ʐς��悶���z
(�A)�@�u�n��v�̔_�n�ʐςɐ�߂鍇�v�ʐς̊������Q�����T���ȉ�
(�C)�@�u�n��v�̔_�n�ʐςɐ�߂鍇�v�ʐς̊������T�����W���ȉ�
(�E)�@�u�n��v�̔_�n�ʐςɐ�߂鍇�v�ʐς̊������W����
�C�@�O�N�x�܂ł̂����ꂩ�̔N�x�Ɍ�t�v�������Ēn��W�ϋ��͋�����t����Ă���A���A���N�x���܂���t�v���������ꍇ
��t�P���ɂ��ẮA�A�Ɠ����Ƃ��A��t�Ώۖʐς̌v�Z���@�ɂ��Ă�(�P)�̃C��(�A)�Ɠ����Ƃ���B
�A�@���N�x�ɏ��߂Č�t�v���������ꍇ
�ȉ��̌�t�P���ɍ��v�ʐς��悶���z
(�A)�@�u�n��v�̔_�n�ʐςɐ�߂鍇�v�ʐς̊������Q�����T���ȉ�
(�C)�@�u�n��v�̔_�n�ʐςɐ�߂鍇�v�ʐς̊������T�����W���ȉ�
(�E)�@�u�n��v�̔_�n�ʐςɐ�߂鍇�v�ʐς̊������W����
�C�@�O�N�x�܂ł̂����ꂩ�̔N�x�Ɍ�t�v�������Ēn��W�ϋ��͋�����t����Ă���A���A���N�x���܂���t�v���������ꍇ
��t�P���ɂ��ẮA�A�Ɠ����Ƃ��A��t�Ώۖʐς̌v�Z���@�ɂ��Ă�(�P)�̃C��(�A)�Ɠ����Ƃ���B
�P�q�{���́A�I�z�[�c�N�����U���ǒ������t�����{���͋��ɂ��A�u�n��v�y�ѕK�v�ɉ����I�z�[�c�N�����U���ǒ��Ƌ��c�̏�A�n��_�Ƃ̔��W��}��ϓ_����A���̎g�r�����猈�߂邱�Ƃ��ł�����̂Ƃ���B
��T�@�o�c�]�����͋���t����
�@�\�ɔ_�n��݂��t���邱�Ƃɂ��i���͐V�K��
�W���c�_�g�D�Ƃ̊Ԃ�
����_��Ǝ�ϑ��_���������邱�Ƃɂ��j�A
�o�c�]�����̓��^�C�A�����_�Ǝҋy��
�_�n�̑����l�ɑ��A���ɂ�苦�͋�����t������̂Ƃ���B
�ȉ��̂����ꂩ�ɊY������_�n���L�ҁi�l���͖@�l�j�Ƃ���B
(�P)�@�_�ƕ���̌����ɂ��o�c�]������_�Ǝ�
(�R)�@�_�n�̑����l�Ŕ_�ƌo�c���s��Ȃ���
(�P)�@�_�ƕ���̌����ɂ��o�c�]������_�Ǝ҂̏ꍇ
�@�\�ɑ��A�S�Ă�
����n��10�N�ȏ�݂��t���邱�Ɓi���͐V�K�ɏW���c�_�g�D�Ƃ̊ԂŌ_������������ŁA���Y�W���c�_�g�D�ɑ�10�N�ȏ����_��ƈϑ����s�����Ɓj���K�v�ł�����̂Ƃ���B
�������A�ȉ��̎���n���������̂Ƃ���B
�C�@�_�ƐU���n�����10�������i�l�Ȃ��������ʐςƂ���B�j�̎���n
�E�@�@�\����Ȃ���������n�y�ы@�\�ɑ݂��t�������̂̕Ԋ҂��ꂽ�_�n
�G�@���������_�ƕ���̍앨�ȊO�̍앨���͔|���鎩��n
�Ȃ��A�W���c�_�g�D�ɑ�����_��ƈϑ����s���ꍇ�ɂ́A�E���������̂Ƃ���B
�܂��A
���L�_�n�̏ꍇ�ɂ́A�T�N�Ԃ̑ݕt�����p�����ĂQ��s�����ƂƂ���B
(�Q)�@���^�C�A����_�Ǝҋy�є_�n�̑����l�Ŕ_�ƌo�c���s��Ȃ��҂̏ꍇ
�@�\�ɑ��A�S�Ă̎���n��10�N�ȏ�݂��t���邱�Ɓi���͐V�K�ɏW���c�_�g�D�Ƃ̊ԂŌ_������������ŁA���Y�W���c�_�g�D�ɑ�10�N�ȏ����_��ƈϑ����s�����Ɓj���K�v�ł�����̂Ƃ���B
�������A�ȉ��̎���n���������̂Ƃ���B
�C�@�_�ƐU���n�����10�������i�l�Ȃ��������ʐςƂ���B�j�̎���n
�E�@�@�\����Ȃ���������n�y�ы@�\�ɑ݂��t�������̂̕Ԋ҂��ꂽ�_�n
�Ȃ��A�W���c�_�g�D�ɑ�����_��ƈϑ����s���ꍇ�ɂ́A�E���������̂Ƃ���B
�܂��A���L�_�n�̏ꍇ�ɂ́A�T�N�Ԃ̑ݕt�����p�����ĂQ��s�����ƂƂ���B
(�R)�@���^�C�A����_�Ǝҋy�є_�n�̑����l�Ŕ_�ƌo�c���s��Ȃ��҂́A�_�ƌo�c��ړI�Ƃ���
���p���̐ݒ���Ă���_�n���͓���_��Ǝ�ϑ��_��Ɋ�Â��_��Ƃ�������Ă���_�n������ꍇ�ɂ́A�������������邱�Ƃ��K�v�ł�����̂Ƃ���B
(�S)�@
�V�x�_�n�̏��L�҂͂�����������邱�Ƃ��K�v�ł�����̂Ƃ���B
(�T)�@��t�Ώێ҂́A��t�����10�N�ԁA���̂��Ƃ��s���Ȃ����̂Ƃ���B
�A�@�_�ƕ���̌����ɂ��o�c�]������_�Ǝ҂̏ꍇ
�p�~����̌o�c��ړI�Ƃ����_�n�̏��L���◘�p���̐V���Ȏ擾�y�ѓ���_��Ǝ��
�C�@���^�C�A����_�ƎҁA�_�n�̑����l�Ŕ_�ƌo�c���s��Ȃ���
�_�ƌo�c��ړI�Ƃ����_�n�̏��L���◘�p���̐V���Ȏ擾�y�ѓ���_��Ǝ���i�V���ȑ����ɂ��_�n���擾�����ꍇ�A��t�\�����ɑ݂��t���Ă������L�_�n�ɂ��āA�ݎ؊��Ԗ������͍��Ӊ��ɂ��g�p���v���������ꍇ�ɂ́A(�Q)����(�R)�ɏ����ċ@�\�ɑ��_�n��݂��t���閔�͏W���c�_�g�D�ɑ�����_��ƈϑ����s�����Ƃ��K�v�ł�����̂Ƃ���B�j
(�U)�@�@�\�ɑ݂��t�����_�n���A�S���]�݂���Ȃ������ꍇ�ɂ͌�t���s��Ȃ����̂Ƃ���B
�܂��A��t�ΏێҎ��g�����Ȃ̏��L�_�n���@�\�������ꍇ�͌�t�ΏۂƂ��Ȃ����̂Ƃ���B
(�V)�@�@�\���W���c�_�g�D�ɓ���_��ƈϑ������_�n�ɂ��ẮA���Y�W���c�_�g�D���v��Ɋ�Â��@�l���Ɍ�������g�݂��s���Ă���ꍇ�Ɍ����t�ΏۂƂ�����̂Ƃ���B
(�W)�@�{���͋��̌�t�����҂́A���Y��t�����N�x�ȍ~�ɍēx�{���͋��̌�t���邱�Ƃ��ł��Ȃ����̂Ƃ���B
�܂��A�ȉ��̕⏕���̌�t�����ҋy�т��̑����l�́A�{���͋��̌�t���邱�Ƃ��ł��Ȃ����̂Ƃ���B
�˕ʏ����⏞�o�c���萄�i���Ǝ��{�v�j�i����24�N�Q���W���t��23�o�c��2955���_�ѐ��Y���������˖��ʒm�j�ʋL�Q�y�ђS����ւ̔_�n�W�ϐ��i���Ǝ��{�v�j�i����25�N�T��16���t��25�o�c��432���_�ѐ��Y���������˖��ʒm�j�ʋL�P�Ɋ�Â��o�c�]�����͋�
(�X)�@�ȉ��̕⏕���̌�t��������N�x�ɂ͖{���͋��̌�t�����Ȃ����̂Ƃ���B
�C�@�S����ւ̔_�n�W�ϐ��i���Ǝ��{�v�j�i����25�N�T��16���t��25�o�c��432���_�ѐ��Y���������˖��ʒm�j�ʋL�P�Ɋ�Â����U���މ������͋�
��t�v�������_�n�ʐρi�l�Ȗʐς��܂ނ��̂Ƃ���B�j�ɉ����A�ȉ��̋��z����t������̂Ƃ���B
(�Q)�@0.5������2.0�����ȉ�
�A�@�@�\�ɑ݂��t�����_�n�̂����A��M�ł��]�݂����A�@�\�ɑ݂��t������t�ΏۂƂȂ�S�_�n�ʐϕ��ɂ��Č�t�\�����邱�Ƃ��ł�����̂Ƃ���B
�C�@�P�̌�t�Ώێ҂́A��t���悤�Ƃ���N�x�̂R��10���܂łɁA�ȉ��̂����ꂩ�̏��ނ��쐬���A�L�ړ��e�����鏑�ނ�Y�t�̏�A��t�Ώ۔_�n�̖ʐς��ő�ł���s�����ɑ���o������̂Ƃ���B
(�A)�@�_�ƕ���̌����ɂ��o�c�]������_�Ǝ�
�o�c�]�����͋���t�\�����i
�ʋL�l����P���j
(�C)�@���^�C�A����_�Ǝҋy�є_�n�̑����l�Ŕ_�ƌo�c���s��Ȃ���
�o�c�]�����͋���t�\�����i
�ʋL�l����Q���j
�A�@�����́A��t�Ώێ҂����o�̂�������t�\�����̋L�ړ��e����t�v�������Ă��邱�Ƃ��m�F�̏�A�R�̌�t�z����t�Ώێ҂ɑ���t������̂Ƃ���B
��t�Ώێ҂���t�Ώ۔_�n���s�����ɏ��L���Ă���ꍇ�ɂ́A�W����s�����ɂ����ď��������s���A��t�Ώێ҂��ł���������n�����L���Ă���s�������A�S�Ă̎���n���ɂ��Č�t���s�����̂Ƃ���B
(�A)�@�_�ƕ���̌����ɂ��o�c�]������_�Ǝ�
�o�c�]�����͋���t����ʒm���i
�ʋL�l����P�|�P���j
(�C)�@���^�C�A����_�Ǝҋy�є_�n�̑����l�Ŕ_�ƌo�c���s��Ȃ���
�o�c�]�����͋���t�\�����i
�ʋL�l����Q�|�Q���j
�C�@�����́A��t�\�����̐R���ɂ��Ĕ_�ƈψ���y�є_�n���p�W�ω~�����c�̂ƘA�g���A���Ɍ�t�\���҂��V�x�_�n�̏��L�҂��ۂ��ɂ��ẮA�_�ƈψ���Ɋm�F������̂Ƃ���B
(�P)�@�����́A�o�c�]�����͋��̌�t�����҂��A��t�����10�N�ȓ��ɁA��t�v�������Ȃ��Ȃ������Ƃ����炩�ƂȂ����ꍇ�ɂ́A��t���s�����o�c�]�����͋�����t�Ώێ҂ɕԊ҂�������̂Ƃ���B
(�Q)�@���̂����ꂩ�ɊY������ꍇ�́A�Ԋ҂���K�v�͂Ȃ����̂Ƃ���B
�A�@
�y�n���p��@�\�@��20���̋K��ɂ��_�n���@�\����Ԋ҂��ꂽ�ꍇ����ނȂ�����̂���ꍇ
�C�@����_��Ǝ�ϑ��_��ɌW���t�Ώ۔_�n�ɂ��āA�@�\�ɓ��Y����_��Ǝ�ϑ��_��̎c�����Ԉȏ�̊��Ԃ��@�\�ɑ݂��t���邽�߂ɁA���Y����_��Ǝ�ϑ��_�������ꍇ
�@�\����Ⴕ���͏��L���Ă���_�n�Ⴕ���͎؎��]�҂��k�삷��_�n�̗אڔ_�n���@�\�ɑ݂��t�������Y�אڔ_�n�̏��L�Җ��͓��Y�אڔ_�n���@�\�ɑ݂��t�������_�ɂ����ē��Y�אڔ_�n���k�삵�Ă����_�Ǝҋy�тQ�M�ȏ��
���ڂ���_�n���@�\�ɑ݂��t�������Y�_�n�̏��L�Җ��͓��Y�_�n���@�\�ɑ݂��t�������_�ɂ����ē��Y�_�n���k�삵�Ă����_�Ǝ҂ɑ��A���ɂ�苦�͋�����t������̂Ƃ���B
�ȉ��̂����ꂩ�ɊY������҂Ƃ���B
(�P)�@�Q��(�P)�ɒ�߂��t�Ώ۔_�n������n�ł���ꍇ
��t�Ώ۔_�n���@�\�ɑ݂��t�����_�n���L�҂ł���_�Ǝ�
(�Q)�@�Q��(�P)�ɒ�߂��t�Ώ۔_�n���ݎؒn�ł���ꍇ
��t�Ώ۔_�n�̏��L�҂��@�\�Ɍ�t�Ώ۔_�n��݂��t����ۂɗ��p����L���Ă����
(�P)�@�ȉ��̂����ꂩ�ɊY������_�n�i�ȉ��u��t�Ώ۔_�n�v�Ƃ����B�j�ł�����̂Ƃ���B
�A�@�ȉ��ɗאڂ���_�n�i�����Ɍ�t�\�������ꍇ�́A�אڂ���_�n�ɗאڂ���_�n���܂ނ��̂Ƃ���B�j
(�A)�@�@�\�����L�����͒��ԊǗ������擾���Ă���_�n
(�C)�@�@�\�@��17���Q���̋K��Ɋ�Â����\���ꂽ�؎��]�҉�����ɋL�ڂ��ꂽ�؎��]�ҁi�ȉ��u�؎��]�ҁv�Ƃ����B�j���o�c����_�n
�C�@�ȉ��̂����ꂩ�ɊY������A��A�̔_��Ƃ̌p���Ɏx�Ⴊ�����Ȃ��_�n
(�A)�@�l�ȂŐڑ�����Q�M�ȏ�̔_�n
(�C)�@�_�����͐��H��������ŗאڂ���Q�M�ȏ�̔_�n
(�E)�@�e�X����Őڑ�����Q�M�ȏ�̔_�n
(�G)�@�i��ɐڑ�����Q�M�ȏ�̔_�n
(�I)�@�؎��]�҂̑�n�ɐڑ����Ă���Q�M�ȏ�̔_�n
(�Q)�@��t�Ώ۔_�n�̏��L�҂��A���Y��t�Ώ۔_�n��10�N�ȏ�@�\�ɑ݂��t������̂Ƃ���B
�܂��A���L�_�n�̏ꍇ�ɂ́A�T�N�Ԃ̑ݕt�����p�����ĂQ��s�����ƂƂ���B
(�R)�@��t�Ώ۔_�n���A�@�\����؎��]�҂ɑ��݂��t��������̂Ƃ���B
(�S)�@�P��(�P)�̔_�n�����L�Ҏ���@�\�������ꍇ�y�тP��(�Q)�̔_�n���@�\�ɑ݂��t������ȑO�ɗ��p����L���Ă����҂��Ăы@�\�������ꍇ�͌�t�ΏۂƂȂ�Ȃ����̂Ƃ���B
(�T)�@
�ʕ\�Q�Ɍf���闬�����ɌW��⏕���̌�t�Ώ۔_�n�ɂ��ẮA���Y�⏕���̌�t�v���ł��闘�p�����ݒ���ԓ��͖{���͋��̌�t�Ώ۔_�n�Ƃ��Ȃ����̂Ƃ���B
�������A�i�o�����ł���j��t�Ώ۔_�n�ł���A���A�i���ł���j�K�͊g����Z�y�ыK�͊g���t���̌�t�Ώ۔_�n�łȂ��ꍇ�́A���p����L���Ă���҂ɑ���{���͋��̌�t�Ώ۔_�n�Ƃ�����̂Ƃ���B
(�U)�@��t�Ώ۔_�n���ݎؒn�̏ꍇ�ɂ́A���Ӊ�����،����͎g�p�ݎ،����ݒ��P�N�ȏ�o�߂��Ă���A���A�����̂P�N�ȏ�O�ł�����̂Ƃ���B
(�V)�@�ȉ��̂����ꂩ�̋��͋��A�x�����̌�t�����҂͖{���͋��̌�t�����Ȃ����̂Ƃ���B
�C�@��T�̂Q��(�W)�ɋL�ڂ����o�c�]�����͋�
��t�v�������_�n�ʐρi�l�Ȗʐς��܂ނ��̂Ƃ���B�j�ɉ����A�ȉ��̋��z����t������̂Ƃ���B
��t�v�������_�n�̍��v�~2.0���~�^10��
(�Q)�@����28�N�x�y��29�N�x�̌�t�z
��t�v�������_�n�̍��v�~1.0���~�^10��
��t�v�������_�n�̍��v�~�T��~�^10��
��t�Ώێ҂́A��t���悤�Ƃ���N�x�̂R��10���܂łɁA���Ɍf����\�������쐬���A�L�ړ��e�����鏑�ނ�Y�t�̏�A�����ɒ�o������̂Ƃ���B
(�A)�@��t�Ώ۔_�n������n�̏ꍇ
�k��ҏW�ϋ��͋���t�\�����i
�ʋL�l����S���j
�k��ҏW�ϋ��͋���t�\�����i
�ʋL�l����T���j
�A�@�����́A��t�Ώێ҂����o�̂�������t�\�����̋L�ړ��e����t�v�������Ă��邱�Ƃ��m�F�̏�A�R�̌�t�z����t�Ώێ҂ɑ���t������̂Ƃ���B
(�A)�@��t�Ώ۔_�n������n�̏ꍇ
�k��ҏW�ϋ��͋���t����ʒm���i����n�j�i
�ʋL�l����S�|�P���j
�k��ҏW�ϋ��͋���t����ʒm���i�ݎؒn�j�i
�ʋL�l����T�|�P���j
�C�@�����́A��t�\�����̐R���ɂ��Ĕ_�ƈψ���y�є_�n���p�W�ω~�����c�̂ƘA�g���A���Ɍ�t�\���҂��V�x�_�n�̏��L�҂��ۂ��ɂ��ẮA�_�ƈψ���Ɋm�F������̂Ƃ���B
(�P)�@�����́A�k��ҏW�ϋ��͋��̌�t�����҂��A��t�����10�N�ȓ��ɁA��t�v�������Ȃ��Ȃ������Ƃ����炩�ƂȂ����ꍇ�ɂ́A��t���s�����k��ҏW�ϋ��͋�����t�Ώێ҂ɕԊ҂����邱�ƂƂ���B
(�Q)�@�y�n���p��@�\�@��20���̋K��ɂ��_�n���@�\����Ԋ҂��ꂽ�ꍇ����ނȂ�����̂���ꍇ�́A�Ԋ҂���K�v�͂Ȃ����̂Ƃ���B
��V�@�_�n�������ɌW��⏕���̎戵��
�ʕ\�Q�Ɍf���闬�����ɌW��⏕���̌�t�Ώ۔_�n�ɂ��āA���Y�⏕���̌�t�v���ł��闘�p���ݒ蓙���ԁi
�_�n���p�W�ω~�����c�̖���
���_�n�ۗL�������@�l�Ƃ̊ԂŒ�������
�����ϔC�_����Ԃ��܂ނ��̂Ƃ���B�j���ɓ��Y���p���i�����ϔC�_��j�������ŋ@�\�ɑ݂��t����ꂽ�ꍇ�ł����Ă��A�ȉ��̂����ꂩ�̗v�������Ε⏕���̕Ԋ҂�v���Ȃ����̂Ƃ���B
�P�@�⏕���̌�t�ΏۂƂȂ������p�������A�_�n���L�҂ƍk��҂Ƃ̊Ԃō��Ӊ��邱�ƁA�_�n���L�҂��A�⏕���̌�t�v�������c�����Ԉȏ�̊ԁA���Y�_�n���@�\�ɑ��݂��t���邱�ƁB
�Q�@�⏕���̌�t�ΏۂƂȂ������p�������A�_�n���L�҂ƍk��҂Ƃ̊Ԃ���_�n���L�҂Ƌ@�\�Ƃ̊ԂɈړ]����邱�ƁB
�P�@�I�z�[�c�N�����U���Njy�ьP�q�{���́A�{���Ƃ̎��{�ɍۂ��ē����l���̎戵���ɂ��ẮA
�ʋL�l����P������T�����܂ł̕ʓY�ɂ��K�Ɏ戵���悤���ӂ�����̂Ƃ���B
�Q�@�{���ƂɊ֘A����_�n�Ɋւ���_��́A�S�Ă̊W�҂̍��ӂ̂��Ɛݒ薔�͉���悤�A���ӂ�����̂Ƃ���B
�R�@�o�c�]�����͋��̌�t�Ώێ҂̔_�Ɨp�@�B�̎戵���ɂ��ẮA�W���E�n��̘b�����̒��ŁA�n��S�̂Ƃ��Ă̋@�B�R�X�g������������ϓ_���猟�����邱�Ƃ��]�܂������Ƃɗ��ӂ�����̂Ƃ���B
���̎��{�v�̂́A����27�N�Q��27������{�s���A����26�N�x�̗\�Z�ɌW�鋦�͋�����K�p����B
|
|
�p�� | ��` |
�_�n���ԊǗ��@�\ | �_�n���ԊǗ����Ƃ̐��i�Ɋւ���@���i����25�N�@��101���B�ȉ��u�@�\�@�v�Ƃ����B�j��Q���S���ɋK�肷��u�_�n���ԊǗ��@�\�v�������B |
�l�E�_�n�v���� | �l�E�_�n�������������x�����Ǝ��{�v�j�i����24�N�Q���W���t��23�o�c��2955���_�ѐ��Y���������˖��ʒm�j��Q�̂P�̎��Ɓi�l�E�_�n�v�����쐬���Ɓj�ʋL�P��P�̐l�E�_�n�v�����y�т���玖�Ƃɏ����Ďs�������Ǝ��ɍ쐬�E�X�V�����v�����������B |
�_�ƐU���n�� | �_�ƐU���n��̐����Ɋւ���@���i���a44�N�@����58���j��U���P���̋K��ɂ��w�肳�ꂽ�u�_�ƐU���n��v�������B |
�W���c�_�g�D | �o�c��������������{�v�j�i����22�N�S���P���t��22�o�c��7133���_�ѐ��Y���������˖��ʒm�j�W�̑�P�̂P��(�P)�̇A�̃A�ɋK�肷��u�W���c�_�v�������B |
����_��Ǝ�ϑ��_�� | �_��Ƃ��ϑ����邱�Ƃ���_��̂����A����҂��_�Y���Y���邽�߂ɕK�v�ƂȂ鉺�L�̊�I�ȍ�Ƃ��s�����ƁA���̐��Y�����_�Y���Y����҂̖��`�������Ĕ̔����邱�ƕ��тɂ��̔̔��ɂ������̒��x�ɉ������Y������_��Ƌy�є̔��̎���̑Ή��Ƃ��ď[�����邱�Ƃ�����̂������B �@�@��ɂ��ẮA�k�N�E��~���A�c�A�y�ю��n�E�E�� �A�@���A�哤�ɂ��ẮA�k�N�E���n�A�d��y�ю��n �B�@���̑��̍�ڂɂ����ẮA�@�y�чA�ɏ������� |
�o�c�]�� | �ȉ��Ɍf����_�ƕ���̂����Q�ȏ���o�c����҂��P�ȏ��p�~���邱�Ƃ������B �@�@�y�n���p�^�앨�i��i�����y�тv�b�r�p����܂ށB�j���i�����A���唞�A�Z��唞�A�͂������j�A�哤�A���A�Ȃ��ˁA�Ă�؋y�тł����p�ꂢ����j �A�@�I�n��ؓ��i��A�ꂢ����i�ł����p�ꂢ����������j�A�Â���A���ށi�哤�������j�A�����p�앨�i�q���������j�A�ŁA�����j �B�@�{�ݖ�� �C�@�I�n�ʎ� �D�@�{�݉ʎ� �E�@�I�n�Ԃ� �F�@�{�݉Ԃ� �G�@�� �H�@�q�� �I�@�T�g�E�L�r �J�@���̑��i��L�ȊO�̔_�Ɛ��Y����j �Ȃ��A�@�\�W�ϋ��͋��ɂ�����u�{�݁v�́A�K���X���A�r�j�[���n�E�X�ȂǁA�����E�ۉ��̗e��I�{�݂̒��Ŋe��앨�̐�������ɍ����悤�ɁA���x�A���x�A�Ɠx�Ȃǂ͔̍|����l�H�I�ɍ��o�����Ƃ��\�Ȕ_�ƕ���������A�J�悯�p�핢�A�g���l���͔|�A�}���`�͔|�͊܂܂Ȃ����̂Ƃ���B |
�_�n�̑����l | �@�\�W�ϋ��͋��̌�t����N�x���͂��̑O�N�x�ɔ_�n�𑊑����A�����l����͔_�Ƃ��s��Ȃ��҂������B |
����n | ��t�ΏێҖ��͌�t�Ώێ҂̐��ш����i�_�n�@�i���a27�N�@����229���j��Q���Q���ɋK�肷�鐢�ш����������܂��B�j���A�@�\�ɑ݂��t�������̂P�N�O�̎��_����A���L���Ɋ�Â����炪�p�����čk�얔�͓K���ȊǗ����s���Ă����_�n�i��t�Ώێ҂��_�n�̑����l�̏ꍇ�́A�푊���l�����L���Ɋ�Â�����k�삵�Ă����_�n�ŁA�����ォ��@�\�ɑ݂��t������܂ł̊Ԃɗ��p���̐ݒ�����Ă��Ȃ��������́j�������B �������A�ȉ��̓_�ɗ��ӂ�����̂Ƃ���B �P�@�u�P�N�O�̎��_�v�ɂ��� (�P)�@�ЊQ�̔�����y�n���ǎ��Ɓi��Ր����j�̎��{�ɔ����A�{�l�̈ӎv�Ɋւ�炸�����I�ɍk��s�\�ƂȂ��Ă������Ԃ�����ꍇ�́A���Y�s�k����ԂƘA������k����Ԃ��@�\�ɑ݂��t����������P�N�ȏ゠��Ύ���n�Ƃ��Ď�舵�����̂Ƃ���B (�Q)�@�n��ɂ����鋦�蓙�ɂ��ݎɂ��W�c�]��i�u���b�N�E���[�e�[�V�����B�ȉ��u�a�q�v�Ƃ����܂��B�j���s���Ă����ꍇ�ɂ́A����n�ʐς��ȉ��̂Ƃ����舵�����̂Ƃ���B�������A����̂a�q�n��̔_�ƎґS�Ăɓ���̗v����K�p������̂Ƃ���B �A�@�a�q�ɂ��āA���ɂP���[�e�[�V�����̌v����Ԃ����A�X�Ɍp�����Ď��g��ł���ꍇ�i�C�ȊO�̏ꍇ�j |
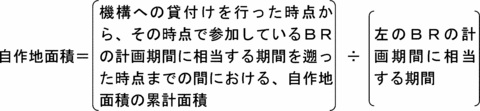
|
�C�@�a�q�ɏ��߂ĎQ�����A�v����Ԃ����Ă��Ȃ��ꍇ |
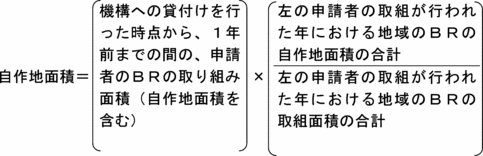
|
�Q�@�u�k�얔�͓K���ȊǗ����s���Ă����v�ɂ��� �_��Ƃ̈ϑ��i����_��ƈϑ����܂݂܂��B�j���܂ނ��̂Ƃ���B |
���L�_�n | �_�ƌo�c��Ջ������i�@�i���a55�N�@����65���B�ȉ��u��Ջ����@�v�Ƃ����܂��B�j��18���R����S�����������̋K��ɂ��A���l�̋��L�ɌW��_�n�ɂ��ė��p���̐ݒ薔�͈ړ]�Ƃ��ċ@�\�ւ̑ݕt�����s�����_�n�������B |
���p�� | �ݎ،��A�g�p�ݎɂ�錠�����͔_�Ƃ̌o�c�̈ϑ����邱�Ƃɂ��擾�����g�p�y�ю��v��ړI�Ƃ��錠���������B |
�V�x�_�n | �_�n�@��32���P���e���̂����ꂩ�ɊY������_�n�������B |
�y�n���p | �y�n���p�@�i���a26�N�@����219���j���ɂ����p�ɂ��@�\�ɑ݂��t���Ă���_�n�����������ꍇ�������B |
�אڂ���_�n | �ȉ��̂����ꂩ�ɊY�������A�̔_��Ƃ̌p���Ɏx�Ⴊ�����Ȃ��_�n�������B �@�@�l�ȂŐڑ�����_�n �A�@�_�����͐��H��������Őڑ�����_�n �B�@�e�X����Őڑ�����_�n �C�@�i��ɐڑ�����_�n �D�@�؎��]�҂̑�n�ɐڑ����Ă���Q�M�ȏ�̔_�n |
�_�n���p�W�ω~�����c�� | ��Ջ����@��11����14�ɋK�肷��_�n���p�W�ω~�����c�̂������B |
���_�n�ۗL�������@�l | �_�Ƃ̍\�����v�𐄐i���邽�߂̔_�ƌo�c��Ջ������i�@���̈ꕔ���������铙�̖@���i����25�N�@����102���j��P���̋K��ɂ������O�̊�Ջ����@��W���P���ɋK�肷��_�n�ۗL�������@�l�������B |
�����ϔC | �_�n���p�W�ω~�����c�̖��͋��_�n�ۗL�������@�l�i�ȉ��u�_�n�W�ω~�����c�̓��v�Ƃ����܂��B�j�Ƃ̊ԂŁA10�N�ȏ���ϔC���ԂƂ��Ĕ_�n�̑ݕt���i�_��ƈϑ����܂݂܂��B�j�̑������w�肹���A���A���̂����ꂩ�̓��e�ɂ��ĈϔC���s���|�����ʂɂ��ӎv�\������Ă���ϔC�_���������邱�Ƃ������B �@�@�U�N�ȏ�i�V��Ջ����@��18���R����S�����������̋K��ɂ��A���l�̋��L�ɌW��_�n�ɂ��ė��p���̐ݒ薔�͈ړ]���s�����Ƃ�ړI�ɔ����ϔC����ꍇ�ɂ͂T�N�j�̔_�n�̗��p���̐ݒ�y�т��̑�����̑I��i����������肵�Ȃ����̂Ɍ���B�j �A�@�U�N�ȏ�̓���_��ƈϑ��_��̒����y�т��̑�����̑I��i����������肵�Ȃ����̂Ɍ���B�j �B�@�_�n���p�W�ω~�����c�̓��ɔ_�n�̏��L�҂��_�n�̗��p����ݒ肵���ꍇ�ɂ́A���Y�_�n�̓]�݂ɂ��ĂU�N�ȏ�i�V��Ջ����@��18���R����S�����������̋K��ɂ��A���l�̋��L�ɌW��_�n�ɂ��ė��p���̐ݒ薔�͈ړ]���s�����Ƃ�ړI�ɔ����ϔC����ꍇ�ɂ͂T�N�j�̗��p���̐ݒ�y�т��̑�����̑I��i����������肵�Ȃ����̂Ɍ���B�j �Ȃ��A�_�n���p�W�ω~�����c�̓����A�_�n�̎�Ƃ̊ԂŌ_����������ۂɁA�n��̍��ӂ̉��ōs����a�q�̎�g�ɂ��U�N�ȏ�̗��p���̐ݒ薔�͔_��ƈϑ��_��̒���������ȏꍇ�́A�a�q�̎�g�v�揑�Ɋ�Â����Ԃ̐ݒ���s�����Ƃ��\�ł�����̂Ƃ���B |
|
|
���Ɓi�⏕���j�� | �ʒm�ԍ��i�_�ѐ��Y���������˖��ʒm�j |
�_�n���p�W�ώ��H���� | ����15�N�S���P���t��14�o�c��7044�� |
�S����_�n�W�ύ��x�����i���� | ����19�N�R��30���t��18�o�c��7559�� |
�_�n�ʓI�W�ώx�����f������ | ����20�N�R��31���t��19�o�c��7865�� |
�ʓI�W�Ϗ����������f������ | ����20�N�R��31���t��19�o�c��7867�� |
�_�n�m�ہE���p�x������ | ����21�N�S���U���t��20�o�c��7160�� |
�_�n���p�W�ώ��� | ����22�N�R��25���t��21�o�c��6901�� |
�_�ƎҌ˕ʏ����⏞���x�i�K�͊g����Z�j | ����23�N�S���P���t��22�o�c��7133�� |
�˕ʏ����⏞�o�c���萄�i���Ɓi�_�n�W�ϋ��͋��j | ����24�N�Q���W���t��23�o�c��2955�� |
�S����ւ̔_�n�W�ϐ��i���Ɓi�_�n�W�ϋ��͋��A�K�͊g���t���j | ����25�N�T��16���t��25�o�c��432�� |